「パパ、お小遣い、いくらくれるの?」 「友達は、ゲームに課金してるのに、うちはダメなの?」
子どもの口から飛び出す、”お金”にまつわるストレートな質問。その度に、あなたは明確な答えを持てずに、言葉を濁してはいませんか?
キャッシュレス化が進み、お金の「価値」が見えにくくなった現代。子どもにどうやってお金の大切さを教えればいいのか。これは、多くの父親が頭を悩ませる、非常に重要で、そして難しいテーマです。
そこで今回、私たちパパ向けコミュニティ『theダディ!』では、会員のパパたちに「お小遣い、どうしてる?」という緊急アンケートを実施。そこには、試行錯誤しながら我が子とお金に向き合う、父親たちのリアルな声が溢れていました。
この記事では、そんな先輩パパたちの声も交えながら、わが子を”お金に強い子”に育てるための、具体的なお小遣いのあげ方・教え方を、徹底解説します。
Step 1:まず決める!「わが家のお小遣い制度」という名の憲法
お小遣いを始める前に、最も重要なのは「ルール」を明確にすること。場当たり的に渡すのではなく、家庭の”憲法”として、パパが主導してルールを決めましょう。
① いつから、いくらあげる?【theダディ! 会員の声】
まず最初の関門が、「開始時期」と「金額」です。これには、様々な意見がありました。
「うちは小学1年生から月500円でスタート。『学年×100円』を基本にして、毎年4月に昇給する仕組みです。自分で計算できるし、進級の楽しみにもなるみたい」(Tさん / 8歳・10歳の息子のパパ)
「低学年のうちは、毎週月曜日に100円を渡す『週給制』でした。月給だと、すぐ使っちゃって月末まで持たないので。お金の管理の練習には、週給制が良かったですね」(Kさん / 9歳の娘のパパ)
「金額で揉めたので、『学年×500円』という世間の相場を参考に、妻と話し合って決めました。ただ渡すだけでなく、その中からノート代の一部を自分で出させるようにしています」(Sさん / 11歳の息子のパパ)
【結論】 開始時期は「小学校入学」が一つの目安。金額は「学年×100円」の月給制か、「学年と同じ数×10円」の週給制(例:2年生なら20円/週)から始める家庭が多いようです。大切なのは、金額よりも「なぜその金額なのか」を子どもに説明し、家庭内で合意することです。
②「定額制」vs「報酬制」どっちがいい?
- 定額制: 毎月決まった額を渡す方法。計画的にお金を使う練習になります。
- 報酬制: お手伝いをしたら、その対価として渡す方法。働くことの価値を学べます。
「うちは基本給(定額制)+歩合給(報酬制)のハイブリッド型です。『食器洗い10円』『お風呂掃除30円』みたいに、メニューを決めています。何もしなくても最低限はもらえるけど、頑張ればもっともらえる。社会の仕組みと同じだと教えています」(Mさん / 10歳の娘のパパ)
【結論】 どちらにもメリットがありますが、『theダディ!』会員のパパたちからは、この「ハイブリッド型」が好評でした。安定した収入(定額)と、労働の対価(報酬)の両方を体験させるのが、現代的なのかもしれません。
Step 2:お金の「使い方」を教える、パパの会話術
お金をただ渡すだけでは、金融教育にはなりません。その使い方に、パパがどう関わるかが重要です。
①「おこづかい帳」で、お金の流れを見える化する
「最初のうちは、レシートを全部取っておかせて、週末に僕と一緒におこづかい帳をつけるのを習慣にしました。何にいくら使ったか、あといくら残っているかが分かると、子どもなりに『来週のマンガのために、今週はこのお菓子は我慢しよう』とか考え始める。感動しましたね」(Yさん / 9歳の息子のパパ)
【パパの関わり方】 完璧さを求めてはいけません。「計算が合わない!」と叱るのではなく、「お、こんなことにお金を使ったんだな。楽しかったか?」と、お金を使った”体験”に興味を示してあげましょう。
②「ほしい物リスト」で、計画性を育てる
高価なゲームソフトなど、すぐに買えないものが欲しいと言い出した時が、最大のチャンスです。
「5000円のゲームが欲しいと言い出した息子と、『目標達成シート』を作りました。毎月のお小遣いからいくら貯金するか、お手伝いを何回すれば目標に届くかを一緒に計算して、壁に貼って。目標が明確になると、子どもの目の色が変わりますよ。自分で貯めたお金で買ったゲームは、本当に大切そうに遊んでいます」(Hさん / 10歳の息子のパパ)
【パパの関わり方】 「そんな高いものダメ!」と頭ごなしに否定するのではなく、「どうすれば手に入るか、一緒に作戦を立てようぜ!」と、子どもの”夢”を応援する最高の軍師になりましょう。
③ キャッシュレス決済の「怖さ」と「便利さ」を教える
高学年になると、交通系ICカードなどでキャッシュレス決済を経験する機会も増えます。
「娘が電車で友達と出かけるようになったタイミングで、交通系ICカードにチャージする時、**『これは、君が頑張って貯めたお小遣いが、”見えない数字”に変わる瞬間だ。便利だけど、使いすぎないように気をつけろよ』**と伝えました。現金と違って、痛みを感じにくいことの怖さは、父親がしっかり教えるべきだと思います」(Oさん / 12歳の娘のパパ)
【パパの関わり方】 便利なツールを禁止するのではなく、その仕組みとリスクを、大人の言葉で冷静に説明することが、情報化社会を生きる子どもを守ることに繋がります。
まとめ:お小遣いは、親子で「社会」を学ぶ最高の教材
お小遣いは、単なるお駄賃ではありません。 それは、子どもが初めて手にする「社会へのパスポート」であり、親子で経済の仕組みや、労働の価値、そして計画性の大切さを学べる、最高の「生きた教材」です。
「結局、一番大事なのは、親、特に父親がお金に対して真摯な姿勢を見せることなのかな、と。節約するところはする、でも家族の思い出にはしっかり使う。その背中を見せることが、一番の教育なのかもしれませんね」 (Nさん / 9歳・11歳のパパ / theダディ! 会員)
まさに、このNさんの言葉に尽きるのかもしれません。 この記事が、あなたと、そしてあなたのお子さんの、未来の経済観念を育む一助となれば幸いです。
そして、もしあなたが他のパパたちのリアルな声をもっと聞きたくなったら、ぜひ、私たち『theダディ!』のコミュニティのドアを叩いてみてください。そこには、あなたと同じように悩み、奮闘する、たくさんの戦友がいます。



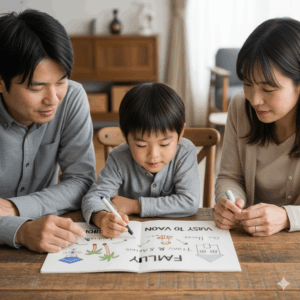



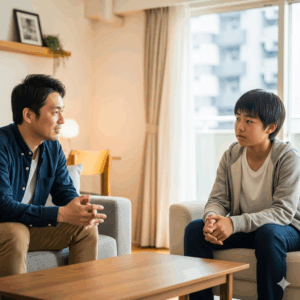


コメント